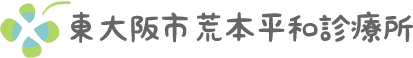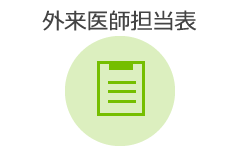院長ブログ
HPVワクチン(子宮けいがん予防ワクチン)の積極的勧奨が再開されます
子宮頸がんは、性交渉によってHPV(ヒトパピローマウイルス)に感染し、持続感染することでがん化する病気です。日本での患者数は年間約1万人、20代後半から増加し40代以降は概ね横ばいになります。早期に発見されれば比較的治療しやすいといわれていますが、がんであることには変わりがなく年間約3,000人が死亡しています。最近では、20代から30代で患者さんが増えています。
日本では、HPVに感染することを予防するHPVワクチンが2013年4月に中学1年生から高校1年生までを対象に定期接種となりました。ところが、その2か月後にワクチン接種後の原因不明の慢性疼痛などを伴う有害事象報告があり、「積極的な接種勧奨」が中止されていました。その後、厚生労働省の専門部会で種々の検討が行われ、2021年11月1日に「積極的な接種勧奨」を再開することが決まりました。
子宮頸がんは命に関わる「ワクチンで予防できる疾患(VPD)」です。日本では副反応ばかりが大々的に報じられがちで、「ワクチンで予防できる疾患(VPD)」のこわさは伝わりません。かけがえのない子どもたちの健康や未来を守るには、接種することのリスクとVPDになることのリスクを比較して冷静に判断することが必要です。保護者だけでなく、ワクチンを受ける思春期の子どもたち自身が予防接種の必要性を十分に理解することも大切です。
HPVワクチンについては「厚生労働省子宮けいがん」で検索すると詳しい情報が手に入ります。かかりつけの先生に相談されるのもよいと思います。
今年のインフルエンザについて-流行する?しない?ワクチン打つ?打たない?-
昨年はインフルエンザの流行はほとんどありませんでした。コロナが流行していたからとかコロナの影響で手洗い・マスクが徹底していたからだとか言われていました。同様にインフルエンザ以外の子どもの感染症も激減していたのですが、今年になってからは昨年流行しなかったRSウイルスが大流行しました。昨年RSウイルスが流行しなかったため免疫のない子どもが多かったからではないかと考えられ、手洗い・マスクの限界が証明されてしまいました。こうなると、同じ理屈で、昨年インフルエンザが流行しなかったので免疫のない人が多いため、今年はインフルエンザが大流行するのではないかと推測する報道もあります。また一方で南半球では2年続けてインフルエンザの流行がなかったことから、日本でも流行はおきないのではないかといわれる専門家もおられます。
昨年はコロナの流行もあり、インフルエンザワクチンの接種が早くからさけばれていましたが、今年はさほど報道されていません。実際、今年のインフルエンザワクチンの出荷量は昨年の7割程度になりそうということで国としてもあまりインフルエンザワクチンの必要性を感じていないのかなと想像しています。コロナと異なりインフルエンザには治療薬もありますしコロナワクチンの接種の方が優先なのかもしれません。
インフルエンザには治療薬がありますが、乳幼児に多い死亡率の高いインフルエンザ脳症にはインフルエンザの治療薬は効果がないためワクチンでかからないように予防することが重要です。子どもの場合ワクチンは2回打たないといけないので早めに1回目を接種することをお勧めします。13歳以上になれば接種は1回で済みますので年内をめどに接種されるとよいでしょう。インフルエンザワクチンが不足する可能性もありますし、コロナワクチン接種との兼ね合いもあります。詳しくはかかりつけ医にご相談ください。
子どもは新型コロナワクチンを打った方がいい?
日本では12歳以上であれば新型コロナワクチンが打てます。新学期が始まることで中学生や高校生をお持ちの親御さんは打たそうかどうしようかと迷っておられることと思います。重篤な基礎疾患のある子どもは新型コロナが重篤化する恐れがあるので日本小児科学会も主治医と相談した上での接種をすすめています。健康な子どもは新型コロナにかかっても重篤化することは少ないものの最低10日間は自宅療養が必要になること後遺症の例もあることから、接種による副作用を考慮しても打つ意味はあると考えられています。
ただ、家庭内感染の場合はやはり親から子への感染が圧倒的に多く、海外の学校でのクラスターの事例でも先生がマスクをしなかったことで生徒が感染したというように、子どものワクチン接種を考えるうえでは周囲の大人がまずワクチン接種を完了していることが重要だと考えられています。
中高生の親御さん、そしてワクチンを打てない12歳未満のお子さんをお持ちの親御さんは是非ワクチン接種を検討してください。
RSウイルス感染症について
RSウイルス(RSV)がまだ流行しています。RSVの流行が騒がれるのは、乳幼児とくに生後6か月以内の乳児で細気管支炎、肺炎をおこし、呼吸困難のため入院する場合があるためです。実際に入院するのはRSVに感染したこどもの1%程度ですので、むやみに心配する必要はありませんが、小さく生まれた赤ちゃん(低出生体重児)や、心臓に穴が開いている赤ちゃん(先天性心疾患)は重症化するといわれています。
現在のところRSVにはインフルエンザに対するような特効薬はなく、ワクチンもありません。ただ、先ほどお話しした重症化すると思われる赤ちゃんには予防的に抗体製剤が定期的に投与されています。
風邪かなと思っていても、咳がどんどんひどくなる、ゼーゼー・ヒューヒューいっている、横になって寝むれない、息づかいが粗い、肩で息をしている、などの呼吸困難が疑われる症状があれば早めに受診しましょう。
コロナワクチン打ちました
医療従事者としての優先接種ということで、4/29に1回目、5/20に2回目を東大阪の病院で打ってきました。特に2回目は発熱や全身倦怠感で仕事に影響が出るのではないかと心配していたのですが、注射した部位の痛み以外は何もなく済みました。私も含め年齢の高い人は全身の副作用が少ないようで、5/17に診療所で接種した75歳以上の10人の方もまったく問題ありませんでした。
大規模接種センターができ、ファイザー社以外に新たに2種類のワクチンが承認されます。診療所でも徐々に接種人数を増やしていこうと思っています。
4月から保育所に行く子どもさんをお持ちのお母さんへ、
例年、4月に入りしばらくすると、熱をだしたり、下痢や嘔吐で体調をくずす子どもたちが増えてきます。その中のかなりの割合を4月から保育所生活をスタートした子どもたちが占めます。その理由は、保育所で今までかかったことのない色々なウイルスによる病気をもらってくるからですが、新型コロナの対策のためか昨年は少なかった気がします。それでも、診察室でお母さんは、「何のために保育所に入れたかわからへん」となげき、おばあちゃんは「やっと、孫の面倒みんで済むようになったと思ったのに、前より大変や」とぼやくことになります。ひどいときは、元気になって保育所に行ったと思ったらもう次の日に熱をだすなんてこともあります。「コロナちゃうやろか?」、「今までこんなにもしょっちゅう熱ださへんかったのに、何か悪い病気ちゃうやろか?」と心配される家族の方もおられますが、いつかは罹る病気に今なっているわけで、保育所から連絡がなく、かかりつけの先生が何も言わなければ大丈夫です。
新型コロナワクチンについて
ニュースでよく見る新型コロナワクチンの名前をご存知ですか?
ファイザー株式会社が販売しており、販売名を「コミナティ筋注」といいます。ニュースではポツポツ副反応のニュースが流れていますが、実際はどうでしょう。ワクチンも含めお薬が世の中に出るまでには治験といってある程度の人数のボランティアにお薬を投与してその有効性と安全性を確かめる試験が行われます。このコミナティでも販売前に国内で試験が行われており、添付文書(「コミナティ添付文書」でネット検索できます)にその成績が記載されています。
日本国内で20歳以上85歳以下の156例(接種群:116例、非接種群:40例)が参加した試験結果です。副反応についてだけ簡単に紹介します。接種部位の疼痛は接種当日から翌日にかけて出てきて、2日間くらい続きます。その頻度はワクチンを接種した人の8割程度で、日常生活に支障が出た方が2例(1.7%)おられました。その他の副反応は接種翌日に出て1日続く程度で、1回目より2回目の方が頻度は高く2回目接種後の副反応と頻度、そのうち日常生活に支障が出た頻度は次の様でした。疲労60%(うち3.4%の人が日常生活に支障が出た)、頭痛44%(1.7%)、筋肉痛16.4%(0%)、悪寒45.7%(1.7%)、関節痛25%(1%)、発熱38%(0.9%)。
この成績をみるとインフルエンザワクチンより副反応の頻度は明らかに高いように思えますが、個人をそして社会を守るために新型コロナウイルスと戦う唯一の武器であることを考えると許容すべき範囲ではないでしょうか。
日本脳炎のワクチンの供給量が減ります
日本脳炎ワクチンを生産している大手のワクチンメーカーが製造上の問題を理由に今年の4月から製品の出荷を停止すると1月15日に発表しました。このために、日本脳炎ワクチンの供給量が昨年と比較すると4月~6月は昨年の4割程度、7月~9月は7割程度に減少します。厚生労働省からは、供給量が安定するまでは、3歳以降で受ける1期の2回接種を優先するようにとの通達が来ています。但し、定期接種で受けられる年齢(3回までは7歳半まで、4回目は12歳まで)が近づいてきている場合はその年齢をすぎないように接種することとなっています。
日本脳炎のワクチンはついつい忘れがちですが、一度、母子手帳を確認して抜けているようであれば、かかりつけの先生に相談してください。
たまにはこんな話も
「そろそろブログの原稿を書かないと」と思っていたら、日本テレビの「スッキリ」ですごくいい話題が紹介されていたのでそのことを書こうと思います。いつも、病気やワクチンのことばかり書いているのでたまにはこんな話も・・・
子どもからサンタさんへの「こんなプレゼントください」のお手紙の話題だったのですが、一つ目は女の子がお母さんへの「いつも有難うという感謝の花束」をサンタさんにお願いしています。そして自分へのプレゼントじゃないのでサンタさんをだますことになってはいけないので、あらかじめママへのプレゼントということを言っておきます。というお手紙でした。
二つ目はこれも女の子から離乳食をはじめた弟へ「焼き芋」をプレゼントしたいとのお手紙。弟がサツマイモのペーストを一番喜んでたべるからとのことでした。
二人とも自分へのプレゼントではなくお母さんや弟君へのプレゼントのお願い、いい話ですよね。
ワクチンの接種間隔のルールが変更になっています
9月末までは、不活化ワクチンの接種後6日以上、生ワクチンの接種後27日以上あけないと、次のワクチンはうてませんでしたが、10月1日からは、注射の生ワクチンの後に注射の生ワクチンをうつ場合は27日以上あけないといけませんが、それ以外の組み合わせの場合は間隔をあけずにうてるようになりました。
例えば、今まではBCGは保健所で、他のワクチンは診療所でうつ場合、BCGの接種日が固定されているため、ワクチンのスケジュールの変更が必要なことがたまにありましたが、これからはそのようなことがなくなります。また、インフルエンザのワクチンの時期に他の定期接種のワクチンが重なった場合もスケジュールの組み方が楽になります。
ただし、インフルエンザを2回うつ場合の間隔やヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンなど何回かうたなければいけないワクチンの接種間隔は決められた通りにする必要があります。
くわしいことはかかりつけの先生に聞いてください。