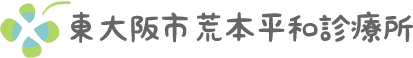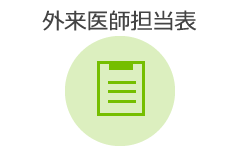院長ブログ
川崎病について
赤ちゃんが熱を出す場合、たいていは咳や鼻水をともない風邪であることが多いのですが、咳も鼻水もなく、熱が続く場合、気をつけておかなければならない病気の中に「川崎病」があります。この病気は、川崎富作先生という日本人が見つけた病気で、世界中で「Kawasaki disease」という病名が使われています。川崎病の場合、心臓を栄養する冠動脈というところに炎症が起こり、一部の人ですが、動脈瘤ができて心筋梗塞を起こす場合があります。この冠動脈の病変を防ぐために、熱が出始めて7日までにガンマグロブリンを点滴することが推奨されています。
川崎病にはいくつかの特徴的な症状があり、6つの症状のうち5つがそろえば川崎病と診断されます。その症状とは①5日以上続く熱②目の充血③真っ赤な唇、イチゴのような舌④発疹⑤手足が赤くなりテカテカパンパン⑥首のリンパ節が腫れるの6つですが、これ以外に赤ちゃんではBCGをした周囲の皮膚が赤くなることも川崎病の診断に役に立ちます(下図)。症状の中には診察の時には消えてしまっていることもあるのでご家族からのお話しが大事です。

手足口病が流行っています
手足口病が流行っています
いま、保育所を中心に手足口病が流行っています。国立感染症研究所の7月11日の発表では、1医療機関あたりの患者報告数が3.53人で昨年同期比の約7倍になったとのことです。大流行した一昨年に迫る水準で、とくに、西日本で流行しているとのことです。
手足口病はウイルスが原因で、感染から3-5日後に2-3ミリの発疹が口の中や手のひら、足底などに出る病気で、約3分の1に発熱がみられます。ワクチンや予防薬はありませんが、大半は数日で治るとされています。
今年の、手足口病は例年と異なって、手のひらや、足の裏の発疹より、肘や膝の周りにたくさん出て、時には体中に発疹がひろがり、発疹が水疱といって水をもつことがあるので、水ぼうそうと間違えそうになることもあります。また、水疱がすごく大きいのもいつもと違うところです。
手足口病では症状が消失した後も2〜4週間にわたって便などからウイルスがずっと排泄されるため、一定期間の「出席停止」の措置はとられません。流行を防ぐには普段からのこまめな手洗いが重要ですが、現実的には、なかなかむつかしいでしょうね。
みずいぼについて
みずいぼについて
プールの季節が近づくと「みずいぼ」の相談が増えてきます。「取るか」「取らないか」が悩ましいところです。
ネットでの726名の医師を対象にアンケートしたところ、「基本的に摘除」「どちらかと言えば摘除」の「取る」派が42.1%、「基本的に保存療法」「どちらかと言えば保存療法」の「取らない」派が37.1%と差がありませんでした。診療科別では、小児科(66人)は「取らない」派の割合が6割以上と多く、皮膚科(42人)は「取る」派が8割近くを占めていました。結局のところ「どっちなの?」ということになりますね。
取らないといけなくなる一番の理由は「プールに入れない」ということだと思いますが、これに関しては、日本小児皮膚科学会が「「みずいぼ」はプールの水ではうつりませんので、プールに入っても構いません。ただし、タオル、浮輪、ビート板などを介してうつることがありますから、これらを共用することはできるだけ避けて下さい。プールの後はシャワーで肌をきれいに洗いましょう。」という統一見解を出しています。
結局のところ、保育園や幼稚園、学校が「みずいぼ」とらなくてもプールに入れますと言ってくれて、お父さん、お母さんもうつってもしかたないなと思ってくれれば、子どもさんが痛い目をしなくて済むようになるんですがね・・・・
かぜに抗生物質は効かない
かぜに抗生物質は効かない
「風邪に抗菌薬(最近は抗生物質のことをこう呼びます)は効かない。」と聞いて「えーーーーー」と思う方、「当たり前やん」と思う方、どちらもおられると思います。
実際、私が医者になりたての時は、高い熱がでていれば抗生物質を処方するのが当たり前でしたし、「風邪だけど、ばい菌の感染がおきてくるかもしれないので抗生物質もだしときますね」と言っていました。
でも、最近では、風邪のほとんどはウイルスが原因なので抗生物質は効き目がなく、出さないのが普通になってきて、外来で「どうしても抗生物質がほしい」と言われるお母さんもほとんど見かけなくなりました。
厚生労働省も遅まきながら、「抗微生物薬の適正使用の手引き」をもうすぐ出し、その中で「かぜに抗菌薬を使うな」と言っています。まず、この手引きではかぜのことは感冒と称し、「発熱の有無は問わず、鼻症状(鼻汁、鼻閉)、咽頭症状(咽頭痛)、下気道症状(咳、痰)の3 系統の症状が「同時に」、「同程度」存在する病態を有するウイルス性の急性気道感染症を、感冒に分類し、感冒に対しては、抗菌薬投与を行わないことを推奨するとしています。つまり、「せき、はなみず、のどの痛みが同じ時期に同じ程度にあれば、それはかぜで抗生物質はいらない」ということです。
ただ、一度よくなっていたのに、症状が再度出現してくるような、経過が思わしくない場合は、抗生物質の投与が必要な場合もありますので、再度、受診するようにしてください。
予防接種について(3)
予防接種について(3)
前回の予防接種(2)では、生後2か月からの予防接種についてお話ししました。順調にいくと生後7~8か月までには一通りの予防接種が終了します。ここで、しばらくお休みですが、1歳になると、次の予防接種の時期となります。今回は1歳になったら受ける予防接種のお話しです。
1歳のお誕生日をすぎれば、MRワクチン(麻しん、風しん混合ワクチン)、水痘ワクチン、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンの4つを接種するのが一般的です。水痘ワクチンは6-12か月あけてもう1回接種します。これは、1回だけでは免疫が十分につかないためです。
4種混合ワクチンも接種できますが、小児科学会推奨の標準的接種の時期は3回目を接種してから12-18か月の間となっているので少し時期が遅くなります。水痘の2回目と時期をあわせるといいかもしれません。
以上が定期接種のお話ですが、最近では任意接種のおたふくかぜワクチンを接種希望される方も増えてきています。接種するかどうか、かかりつけの先生と相談してみてください。
4月から保育所です
4月から保育所です
4月に入りしばらくすると、熱をだしたり、下痢や嘔吐で体調をくずす子どもたちが増えてきます。その中のかなりの割合を4月から保育所生活をスタートした子どもたちが占めます。その理由は、保育所で今までかかったことのない色々なウイルスによる病気をもらってくるからで、診察室でお母さんは、「何のために保育所に入れたかわからへん」となげき、おばあちゃんは「やっと、孫の面倒みんで済むようになったと思ったのに、前より大変や」とぼやくことになります。ひどいときは、元気になって保育所に行ったと思ったらもう次の日に熱をだすなんてこともあります。「今までこんなにもしょっちゅう熱ださへんかったのに、何か悪い病気ちゃうやろか?」と心配される家族の方もおられますが、いつかは罹る病気に今なっているわけで、かかりつけの先生が何も言わなければ大丈夫です。
予防接種について(2)
予防接種について(2)
前回は、一般的な予防接種についてのお話をしました。今回は、生後2か月からの予防接種について具体的にお話しします。
生後2か月というのは、1月5日生まれの赤ちゃんなら3月5日、5月11日生まれの赤ちゃんなら7月11日から予防接種ができるということです。2か月後の誕生日という言い方をする場合もあります。
生後2か月から受けることができる予防接種には、定期接種(自己負担金なし)として、肺炎球菌ワクチン、ヒブ(インフルエンザ菌B型)ワクチン、B型肝炎ワクチンがあり、任意接種(100%自己負担)としてロタウイルスワクチンがあります。肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンは2013年4月から、B型肝炎ワクチンは昨年4月から定期接種になりました。
これまでは、予防接種のスタートは生後3か月の3種混合ワクチン(ジフテリア、百日咳、破傷風)でしたが、いまではこれに不活化ポリオワクチンを加えた4種混合ワクチンが定期接種として生後3か月から受けられます。また、保健センターで生後5か月から受けるBCGもありますね。
ワクチンはできるだけ早めに打ったほうが良いのですが、ワクチンの組み合わせ、接種間隔、接種の期限などのルールがたくさんあり、スケジュールを立てるのが初めてのお母さんにはとても難しいと思います。予防接種を機会にかかりつけの先生を決めましょう。そして、そのかかりつけの先生と、早めに相談されるとよいと思います。
予防接種について(1)
予防接種について(1)
最近は、生後2か月から、たくさんの予防接種を受けることになっています。予防接種のやり方にはいくつかの決まりごとがあり、そのルールを守るために、両方の二の腕の上と下で計4か所、それでもたりなくて太ももにも注射することもあります。
赤ちゃんが可哀想。そんなに一度にたくさん注射して大丈夫?そもそも、予防注射って必要なの?副作用は心配ないの?という、おとうさん、おかあさん、おられますよね。ご両親は打つ気でも、おじいちゃんやおばあちゃんが「わしらは、予防注射なんかせんかったし、わしらの子供もうけへんかったけど、元気に育っとる。ワクチンの怖い話も聞いてるし、打たんとき。」という場合も、まれに聞くことがあります。
一方で、何も考えずに、保健所から言われたし、とか、1カ月検診で言われたしで予防接種を受けに行く親御さんもおられます。これ、大正解です。
予防接種、特に「定期接種」になっているワクチンは、何も考えずに打ってください。「任意接種」のワクチンはかかりつけの先生と相談して決めましょう。
熱が出た(2)
熱がでた(2)
こどもが熱、特に高い熱をだすと、親御さんは心配されます。心配の理由はもちろんこどもがしんどそうにすることですが、それ以外にいくつか理由があります。以前に小児科の雑誌に、お母さん方を対象に「お子さんに熱がでたとき、何が一番心配ですか?」というアンケートをした結果がでていました。順位は忘れましたが、以下のような解答がありました。
「肺炎じゃないか」、「ひきつけないか」、「頭がおかしくならないか」、「何か怖い病気じゃないか」、「脱水症にならないか」などです。
高い熱が急に出ると、熱の原因にかかわらず「熱性けいれん」といって、ちいさなこどもさんはひきつけることがあります。かくいう私も、小さい時に「熱性けいれん」をおこし、あわてた母親が裸足で道に飛び出して近所のおじさんの自転車でお医者さんに飛び込んだという話をしていました。この「熱性けいれん」については、またの機会に詳しくお話しします。
この「ひきつけ」以外のお母さんの心配は「熱は原因ではなくて結果なので、熱の症状だけで心配しなくてもいいですよ。」が正解です。つまり。熱がでるから肺炎になったり、頭がおかしくなったり、怖い病気になったり、脱水症になったりするわけではありません。いずれにしても、何か心配なことがあれば、お医者さんに行ったときに「肺炎じゃないですか?」「頭大丈夫でしょうか?」と聞かれたらいいと思います。熱がでたときの一番の心配事はお母さんによって違いますから。
熱が出た(1)
熱がでた(1)
こどもはしょっちゅう熱を出します。特に、保育所に行きかけた時など、何のために保育所に預けたのかわからないぐらい熱を出して保育所をお休みしないといけなくなります。
たいていの場合、37.5度以上の熱があると保育所に預けられません。予防接種も37.5度以上あると受けられません。予防接種の場合、法律で「明らかな発熱がある場合は予防接種をしてはいけない。」となっており、この「明らかな発熱」が37.5度以上とはっきり書いてあるのです。発熱はいろいろな病気の前ぶれの可能性があることから、予防接種は避けましょうという意味ですが、保育所に行けなくなるのもこれと関係しているのかもしれませんね。
ただ、多くのお母さんは、「37.5度くらいなら大丈夫じゃないかな。」と思っておられるでしょうし、以前にご紹介した小児科学会のホームページでもこどもの発熱は38度以上になっており、熱があっても生後3カ月以上で、機嫌がよく、活気があり、水分が取れていれば、かかりつけの先生の診療時間まで待って受診して大丈夫となっています。
では、どんな時にすぐ診察に連れていったほうがよいのでしょう。正解は「お母さんがすぐ診てもらったほうがいいと思ったとき」です。言葉を変えると「この子いつもと様子が違う、なんか変」とお母さんが思ったときはすぐ診てもらいましょう。もちろん、救急病院にいったら、本人ケロッとしていて、何もなかったなんてこともあるかもしれませんが、自分の子供での経験も含め「母親の何かおかしい。」は、あたっている確率が高いように思います。